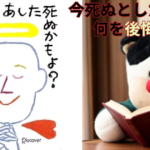さて、昨今この「インフレ」なる化け物が、吾輩の住む牧場にも忍び寄ってきている。人間どもが騒いでいるのを横目に、吾輩なりに観察してみた結果を報告しよう。あれほどまでに日本の経済を襲ったデフレと言う価格競争の時代は過ぎ去り、物価が五月雨式に上がっていくインフレーションの時代がついにこの日本にもやってきてしまったのだ、ヤァヤァヤァ。
しかもだ、しかもだよ。このインフレのご時世において実質的な労働賃金は一向に改善していかない。これをスタグフレーションというのだろう。
ではこの不遇なる時代において生き残るにはどうしたらいいのかを考え見たい

銀行預貯金という名の落とし穴
人間どもは愚かにも、自分たちの草(お金のことらしい)を銀行という名の小屋に預けて安心しているようだ。まるで狼に羊を預けるようなものである。いや、狼の方がまだ正直だろう。少なくとも羊を食べると最初から宣言している。
銀行は違う。「大切にお預かりします」などと殊勝なことを言いながら、実は密かに草を食べているのだ。いや、正確には草の価値を目減りさせているのである。
メカニズムはこうだ。例えば今年、干し草1束が100円だったとしよう。銀行に100円預けて、年利0.01%をもらったところで、来年には100.01円にしかならない。ところがインフレが2%進行すれば、同じ干し草1束は102円になっている。つまり、銀行に預けた100.01円では、もはや干し草1束を買うことができないのだ。01円利息をもらって2年食糧に払ったとしたらその差額が目減りしたことにならないだろうか?
これを人間どもは「実質的な価値の目減り」と呼んでいる。実に巧妙な搾取システムである。単純な話さ。銀行という名の安全資産が、実は今の時代は安全資産とは言い切れないのではないかと吾輩は考えるのだ。
吾輩が特に滑稽に思うのは、人間どもが「元本保証」という言葉に安心しきっていることだ。確かに数字の上では元本は保証される。しかし、その数字が表す実質的な価値は容赦なく目減りしていく。これは「名目的元本保証、実質的元本毀損」とでも呼ぶべきである。
銀行の金庫に札束を詰め込んでも、その札束が買える物の量は年々減っていく。札束という紙切れの枚数は変わらないが、その紙切れの購買力は確実に痩せ細っていく。まさに餓死していく札束である。
投資という名の現実逃避、いや現実直視
このような悲惨な状況を前に、多少なりとも知恵のある人間は「投資」なるものに手を出し始める。吾輩から見れば、これは極めて理にかなった行動である。
なぜなら、投資とは本質的に「インフレとの競争」だからだ。物価が上がるなら、それ以上に資産価値を上げなければならない。当然の理屈である。吾輩たち牛だって、草が不足すれば別の牧草地を探すではないか。
株式投資を例に取ろう。企業は物価上昇に合わせて商品価格を引き上げる。結果として売上も利益も増加し、株価も上昇する傾向にある。つまり株式とは、インフレという嵐に対する避難所のような存在なのだ。
不動産投資も同様だ。物価が上がれば、土地や建物の価格も上がる。家賃も上がる。まるで吾輩たちの牛舎の価値が、周辺の土地開発に伴って上がっていくようなものだ。
さらに言えば、投資は「お金にお金を稼がせる」という魔法でもある。銀行預金が「お金を眠らせる」行為だとすれば、投資は「お金を働かせる」行為である。働かざる者食うべからず、という格言は人間にもお金にも当てはまるのだろう。
ただし、投資にはリスクが付きまとう。これを人間どもは「元本割れの可能性」などと恐れているが、吾輩に言わせれば、銀行預金の方がよほどリスキーである。確実に価値が目減りするのだから。投資のリスクは「かもしれないリスク」だが、預金のリスクは「確実なリスク」なのだ。
分散投資という名の偽善
さて、投資の重要性を理解した人間どもが次に手を出すのが「分散投資」である。特に投資信託という商品が人気らしい。
「卵を一つのカゴに盛るな」という格言に従い、様々な銘柄や資産クラスに資金を分散させる。リスクを下げて安定的なリターンを得る、という触れ込みである。実に模範的で、教科書的で、そして退屈な投資法だ。
吾輩も最初はこの方法を支持していた。我々牛だって、一つの牧草だけでなく様々な草を食べてリスク分散している。理にかなっている、と思っていたのだ。
しかし最近、ある重要な事実に気がついた。分散投資では「金持ちになれない」のである。
分散投資の本質は「平均への回帰」だ。優秀な投資先もあれば、そうでないものもある。結果として全体のリターンは市場平均に近づく。安定しているが、大きな飛躍もない。まるで牧場の真ん中でモー、モーと鳴いているだけの牛のように、平凡で目立たない存在になってしまうのだ。
投資信託の手数料も問題だ。運用会社という中間搾取業者が、投資家の利益を掠め取っていく。彼らは市場が上がっても下がっても手数料を取る。まるで天候に関係なく牛乳代を要求する悪徳業者のようだ。
さらに言えば、分散投資は「機会損失」という最大のリスクを抱えている。テスラ株が10倍になった時、「ああ、もっと集中投資していれば」と後悔する投資家の数は数え切れない。分散投資は確かにリスクを下げるが、同時にリターンの上限も下げてしまうのだ。
集中投資という名の勇気、いや愚行なのか?
ここまで考えた吾輩は、一つの結論に達した。本当に金持ちになりたければ、「集中投資」しかないのではないか、と。
集中投資とは、選りすぐりの少数銘柄に資金を集中させる投資法である。「卵を一つのカゴに盛れ、そしてそのカゴをしっかりと見守れ」というウォーレン・バフェットの教えに従う方法だ。
歴史を振り返れば、大金持ちの多くは集中投資で富を築いている。ビル・ゲイツはマイクロソフト株に、ジェフ・ベゾスはアマゾン株に、イーロン・マスクはテスラ株に、それぞれ資産の大部分を集中させていた。彼らは分散投資などしていない。
集中投資の利点は明確だ。優秀な投資先を見つけることができれば、リターンは劇的に向上する。10倍、100倍の成長も夢ではない。まるで優秀な種牛に全てを託すようなものだ。当たれば大きいのである。
しかし、である。集中投資には相応のリスクが伴う。選択を誤れば、資産の大部分を失う可能性がある。これは「自己責任」という言葉では済まされない重大なリスクだ。
吾輩が特に強調したいのは、集中投資の成功は「個人のセンス」と「ルール設定」に全面的に依存するということだ。
センスとは、優れた投資先を見抜く能力である。これは経験と勉強、そして直感の賜物だ。まるで優良な牧草地を見分ける牛の本能のようなものかもしれない。しかし人間の場合、この能力には個人差が激しい。天才もいれば、悲劇的に無能な者もいる。
ルール設定とは、損切りラインや投資比率などの規律である。感情に流されず、機械的に従うべきルールだ。例えば「30%下がったら損切り」「総資産の50%まで」といった具合に。この規律なくして集中投資は単なるギャンブルと化してしまう。
吾輩が観察するところ、集中投資で成功する人間は極めて少ない。大多数は自分のセンスを過信し、ルールを軽視し、結果として大損を被っている。まるで崖っぷちで綱渡りをする曲芸師のように、華麗に見えるが実は極めて危険な行為なのだ。
結論:牛なりの投資哲学
さて、長々と人間どもの投資行動を観察してきた吾輩だが、最後に牛なりの投資哲学を披露したいと思う。
第一に、銀行預金だけでは資産は確実に目減りする。これは疑いようのない事実である。インフレという名の隠れた税金が、預金者から富を静かに奪っていく。
第二に、投資は必要悪ではなく、必要善である。インフレと戦うための武器であり、資産を守り育てるための手段である。リスクを恐れるあまり、より大きなリスク(購買力の減少)を見逃してはならない。
第三に、分散投資は安全だが平凡である。金持ちになりたければ、どこかで勇気を持って賭けに出る必要がある。ただし、それは無謀な賭けであってはならない。
第四に、集中投資は諸刃の剣である。正しく使えば強力な武器となるが、間違えば自分を切り裂く。センスとルールという二つの要素が不可欠だ。
最後に、投資に絶対的な正解は存在しない。市場は生き物であり、常に変化している。昨日の勝者が明日の敗者になることもある。重要なのは、自分なりの哲学を持ち、それに従って行動することだ。
吾輩は牛である。人間のように複雑な投資はできないが、草を食み、牛乳を出し、のんびりと暮らしている。時にはこのような単純さこそが、最も賢い投資戦略なのかもしれない。ohゴッド!最適解を示してほしい。
少なくとも、吾輩は自分の価値(牛乳と肉)がインフレと共に上昇していることを実感している。これも立派な「現物投資」ではないだろうか。
投稿者プロフィール