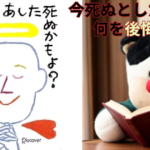さて新総裁に高市早苗氏がなったということで、彼女が何をしようとしているのか、少しでも理解しておくためには経済の基本を今回ご紹介しようとする企画なのだ。
 書生
書生モウモウ先生、最近モノの値段ばっかり上がってますよね。賃金はあがらないし、困りますよね



うん、それをインフレ っていうんだ。物価(モノの値段)がどんどん高くなること。



じゃあ、国が “みんなにお金を配って支えてあげよう” って、日銀がお金を刷って消費税とか減税とかしたらいいじゃないんですか?



いいアイデアに聞こえるけど、気をつけないと危ないのである
ポイント①:インフレがもっとひどくなるかも



今すでに物価が高い状態で、さらにお金をたくさん配ったら、買いたい人が増えるでしょ?
お店は“売れる!”と思って、さらに値段をバーンと上げてしまうかもしれない。値段据え置きだと、お店から商品がなくなってしまうのだ



お菓子が100円→150円になっちゃうみたいなことか!



その通り。だから“ばらまき=減税”をやるのは、インフレ中には慎重じゃないと
ポイント②:借金(国債)を増やすと利子が重くなる



やっぱり国債を使って、国民にお金を配るじゃダメなのかなぁ?



国債は借りているお金だから、利子がつくんだ。今日本にはすでに大きな借金残高があるから、利子を返すお金がどんどん膨らんだら、他の大事なこと(教育・インフラとか)に使えるお金が減ってしまう



なるほど。借金の返すコストが大きくなるなら、借金ばかりはできないな…。「じゃあ、どうすればいいのかな?
ポイント③:逆ノミクスというアイデア
大企業にはしっかり税金を払ってもらう(法人税を増やす)
- 国民が払う消費税を少し下げて、生活が楽にする
- 借金の整理(国債償還)や財政再構築も同時進行する
こうすると、お金を動かしながらもバランスを取ろうっていう戦略なんだ。」



お金持ちには多く払ってもらって、みんなが苦しくならないようにする、ってことだね
ポイント④:アベノミクスの反省
アベノミクスは “円安・金融緩和・企業支援” を組み合わせて、株価を上げて企業を元気にしようとしたけど、国民の実質給料にはあまり届かなかった、という批判があるんだ。」
ポイント⑤:理論と現実のズレ



じゃあ、今は完全に “減税しまくる” のはむずかしいってこと?



そう。デフレの時には増税しちゃダメなのは経済の基礎中の基礎。なのに、政府は10%まであげたよね。デフレって給料あがりません。ってことなのに、増税しちゃったら、余計に財布のひもが固くならない?そんなことは誰でもわかることでしょ。
だけど今みたいなインフレのときには、バランスを取る政策が必要。しかも物価だけ上がって、給料がなかなかあがらないインフレだからちょっと厄介だ。
大企業からの税金、消費税の調整、支援の対象を絞る、借金管理、インフレ抑制も同時に考える必要があるんだ
1. 「お金ってだれが作ってるの?」
みんなが使っている100円玉や1,000円札。これは、銀行やスーパーが作っているんじゃなくて、国(日本)と日銀(にっぽんぎんこう)が作っています。
つまり「お金のプリンター」を持っているのは国なんです。
ちなみにこの本はMMTの基礎を教えてくれる良書。筆者の中野氏の理論にはどの本も納得感が強いと吾輩は考えるのだ
2. 家計(おうち)と国はちがう
よく「国の借金は家計と同じ」と言われるけど、これはちょっとちがいます。
- お母さんに「お小遣いちょうだい」と言っても、お母さんはお金を作れない。だから、働いたり節約したりしてやりくりしないといけない。
- でも、国はちがう。足りなくなったら「新しいお金」を作れるんだ。だから、国は家計のようにお金がなくなって破産することはないんです。
3. 国のお金の使い方(お使いのたとえ)
たとえば、お母さんがあなたにこう言ったとします。
「八百屋さんに行って、にんじんとじゃがいもを買ってきてね」
あなたは1000円を渡されてお店に行きます。お金を払ったら、お店の人に「ありがとう」と言われて、おつりが返ってきます。
このときの流れを国に当てはめると……
- 国がお金を出す →お母さんが自分の財布からお金を出して、あなたに渡す。 あなたがお店でお金を払う
- 国民にお金が回る → お店の人が「ありがとう」と商品とおつりを渡す
- 税金を集める → お母さんがあなたに「余ったおつりは返してね」と言う
つまり、国はまずお金を出して(支出)から、あとで税金(回収)を集めるんです。お母さんが最初にお金を渡さなかったら、あなたは買い物ができないのと同じ。
4. 借金=国民の資産
では「国債(こくさい)」ってなに?
これは国が発行する「借用書」みたいなもの。
たとえばあなたがお母さんに「1000円を貸してね」と言ったとします。あなたは「1年後に返すから」と言ったとしましょう。でもお母さんはきっと忘れてしまうので、「じゃぁ、この紙に証明しておくね」と借用書に書いてあなたへ渡します。これが国債みたいなもの。
でもその紙は、あとであなたがちゃんと返してくれる安心な約束だから、**むしろ宝物(資産)**になります。日本の国債もほとんど日本人が持っているので、「国の借金」は国民にとって「安全なお金の貯金箱」になっているのです。
そしてこの本こそ、漫画と解説の2本立てとなっていて、これをみれば金融の仕組み、MMT理論は何かがわかる。お金はもともとブツブツ交換であったが、何故不便になって今の通貨システムになったのか。謎の異端児経済学者と有名アイドル的な政治家との対決形式で分かり易く書かれています。吾輩お勧めの一冊となる。
5. じゃあ、どこまで使っていいの?
「国はお金をいくらでも作れるなら、無限に使えばいいじゃん!」と思うかもしれません。でもここに大切なルールがあります。
それは インフレ(物の値段がどんどん上がること)。
もしお母さんが「お金は好きなだけあげる!」と言ったら、みんながお菓子を買いすぎて、駄菓子屋さんが「ポテチ1袋1000円!」みたいに値上げするかもしれません。そうなったら困りますよね。
だから国も「物価が上がりすぎないように」気をつけながらお金を使うんです。
超分かり易く説明
あなたがお金をもらって、お菓子を買いに行く話
例えば…
- 今、チョコレートが1個100円。
- ある日、お母さんが「今日は特別に、みんなに100円ちょっと多めに渡すよ。お菓子をたくさん買ってきてね」と言った。
- そのせいでお店に行く人が急に増えて、「それじゃ100円じゃ足りない!200円にしよう」って価格を上げるお店も出てくる。
- だから、もらったお金があっても、「お菓子1個200円」になったら結局あまり買えない。
これが「減税(=みんなにお金を多くあげること)」をすると、物の値段をもっと上げてしまうかもしれない、という話と似ています。
さらに、借金(国債)はこんな感じ。
- お母さんに「この分のお金をちょっと先に借りておいていい?」と言って借りたとする。
- その借りた分はあとで「利子をつけて返すね」と言わなければいけない。
- 利子が大きくなると、「返すときにたくさん返さなきゃいけないから、別のものを我慢しなきゃいけない」ということになる。
だから、減税をするにしても、「今の物価・借金の状態」をちゃんと見ながらやらないと、逆にみんなが困ることになる、という警戒がこの動画の主張なんです。
6. 日本の現実
- 日本はずっと「物が売れない・給料が増えない」=デフレに悩んできました。
- それなのに「給料が増えないからガマンしよう」とお金を出さなかったから、景気が良くならなかった。
PB(プライマリーバランス)の黒字化だと!?とんでもないぜ!
政府は「PBの黒字化を目指します」って言っていたけど、この意味がわかるだろうか?PB?何それ、、、政府が言っているんだから、任せておけばいいや。じゃないのだ!これではこくみんは困るのだ。何故かって?政府の赤字は国民の黒字だからだ。だから政府が黒字化目指すなんてとんでもねーんだよ。
① 政府は「お父さん銀行」
- お父さん(=政府)が毎月おこづかいをくれる。
- 子ども(=国民)はそのおこづかいでお菓子を買ったり遊んだりする。
② お父さんが「赤字」になると?
- お父さん銀行はお金を子どもにいっぱい渡す。
- お父さんの財布は減る(=政府の赤字)。
- でも子どもの財布は増える(=国民の黒字)。
③ 逆にお父さんが「黒字」にしようとすると?
- 「お金を配るのはやめ!むしろ今月は取り上げる!」とやる。
- お父さんの財布は増える(=政府の黒字)。
- でも子どもの使えるお金は減って、お菓子も買えなくなる(=国民の赤字)。
④ ポイント
- 政府と国民は鏡の関係。
- 政府が赤字のとき、国民は黒字になる。
- 政府が黒字にすると、国民は赤字になる。
なるほど。「PB黒字化」(プライマリーバランスの黒字化)がどれだけ“とんでもないこと”なのか、整理して解説しますね。
1. プライマリーバランス(PB)とは?
- 政府の収入(税収など)と支出(社会保障、公共投資など)を比べたとき、借金の元利払いを除いた部分の収支。
- これを黒字化する、というのは「税収だけで支出をまかなう」=「新しい国債を発行しない」という意味。
❶ 政府の赤字は民間の黒字
- 政府が赤字を出して国債を発行し、お金を市中に流す。
- それが企業の売上や家計の所得になり、国民が黒字になる。
- 逆に政府が黒字を目指すと、市場からお金を吸い上げてしまい、国民が赤字になる。
👉「国が財布のひもを締めたら、国民が貧しくなる」のが会計上の真実。
これはさっき説明したからもうわかったね。
❷ 景気を犠牲にしてでも黒字を目指す愚策
- 景気が悪くても、税金を増やす・支出を削ることで「黒字」を目指すことになる。
- これは家庭でいえば「子どもが病気なのに、家計の医療費を削って貯金を増やす」ようなもの。
- 国民生活を削り、成長を妨げる。
3. 国債=借金ではなく、国民の資産
国債は政府にとっての負債ですが、買っているのは国内の銀行や保険会社、個人投資家。つまり国民の資産です。
政府が国債を発行し続けても、日本銀行が円を発行できる限り、返済不能にはなりません。
にもかかわらず「借金だから減らさないと」とPB黒字を目指すのは、国民の資産形成の機会を自ら潰していることになります。
4. 歴史的にも危うい目標
かつて緊縮財政をした国はことごとく経済停滞や失業の増加に苦しんでいます。
EUのギリシャ危機や、平成日本の「失われた30年」はその典型です。PB黒字化を至上命題に掲げて支出を絞った結果、景気は回復せず、むしろ税収が減りました。
PB黒字化は
- 政府の赤字を減らす代わりに、国民の赤字を増やす
- 経済を縮小させ、かえって税収を減らす
- 国民の資産を減らす
- 「百害あって一利なし」の目標
7. まとめ
- 国はお金を作れるから、家計とはちがって破産しない。
- 国がまずお金を出して(支出)、あとから税金を集める。
- 「国の借金」は、実は国民の安全な資産。
- 気をつけるべきなのは「借金の額」ではなく「物価が上がりすぎないかどうか」。
つまりMMTは、
「国はもっと安心してお金を使っても大丈夫。ただしインフレには注意!」
という考え方なのです。
投稿者プロフィール


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10f28e4f.3a52765a.10f28e50.9d061014/?me_id=1220950&item_id=14547649&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_2063%2Fneobk-2775893.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cfd6678.33e73c6f.4cfd6679.4d85509b/?me_id=1409956&item_id=10000262&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbunkyosha%2Fcabinet%2Fitems%2Fgeneral%2F10672194%2Fb_047_1_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1170f3e1.0d8f1ff2.1170f3e2.d6021716/?me_id=1213310&item_id=21248167&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5843%2F9784867165843_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)