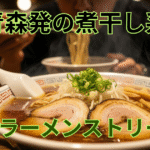PM6時を少し回った木曜の夕刻、吾輩はご主人と共に東京駅地下一階、通称「東京ラーメンストリート」という麺類の聖地へと蹄を進めた。目的地は六厘舎。
あの濃厚魚介つけ麺の殿堂である。ところが、である。店の前には既に人間という生物が長蛇の列をなして、まるで飼料を待つ家畜のごとく並んでいるではないか。木曜日でもこのポテンシャルなのか?吾輩は思わず、自身が食肉として処理される日を想起した。待つことは人生の本質であるが、空腹は哲学を許さない。
ウロウロと、吾輩とご主人は地下街を彷徨った。牧場から逃げ出した牛のように、あるいは食い扶持を探す流浪の民のように。そこで目に留まったのが「津軽煮干 ひらこ屋」である。以前、市谷No.4で煮干という概念に敗北した吾輩としては、ここでリベンジを果たさねばならない。それは牛としての矜持、いや生命体としての尊厳に関わる問題であった。

待ち人1人。これは幸運というべきか、それとも人気のバロメーターとして不安視すべきか。吾輩は5分という時間を、反芻するがごとく思索に費やした。
この店の特徴は、2005年12月に青森で創業し、2025年で20周年を迎えた津軽濃厚煮干しの名店が、ついに東京ラーメンストリートに常設店として県外初出店を果たしたという点にある。平子煮干を中心に4種類の煮干を三段仕込みし、パンチがありながらもあっさりしたスープを特徴とするのだという。三段仕込み、それは牛乳が生乳から加工乳、そして乳製品へと変容する過程を彷彿とさせる。煮干もまた、生から死へ、死から旨味へと昇華する。生命の輪廻とは斯くも残酷で美しい。

ご主人が食券機の前で立ち止まった。「こいくち、千円ね」とご主人は呟いた。吾輩はその横で黙って頷いた。いや、牛は頷けないので、鼻息を荒くしただけである。だいたいラーメン屋は一番オーソドックスなのを頼む。これがしっかりしていないと何を頼んでもきっとダメだろうという吾輩のこだわりのジャッジだ。基本が全てを物語る。それは牧草の質が牛乳の味を決めるのと同じ原理である。
店内に入ると、空気が煮干の香りで満たされていた。

それは海の記憶、小魚たちの最期の叫び、そして旨味への昇華という三位一体の香りである。吾輩は座席に着き、静かにその時を待った。
着丼ドーンだ!!

目の前に現れた一杯は、まるで津軽海峡を煮詰めたような色彩であった。
「スープをまず飲んでみるか」とご主人が言った。吾輩は心の中で「当然である」と応えた。

「ズズズズ……うむ、蓮華を沈めるとサラサラな感じだが、味は薄くはないな」
ご主人の言葉通り、スープは粘度という概念に反逆していた。水のように滑らかでありながら、その味わいは濃密である。それはまるで、吾輩の血液のように見た目は淡泊だが、生命を支える重要な液体として機能する。煮干という小さき生命体が、死後もなお力強く主張する様は、食物連鎖の頂点に立つ人間への痛烈な皮肉である。
「麺はややストレート麺で若干固めだ。スープによく合う」

ご主人が箸を動かしながら語る。吾輩は観察した。確かに、麺は自己主張を忘れていない。柔らかすぎず、硬すぎず、スープに溶解することなく、しかしスープを拒絶することもない。それは社会の中で生きる個人のメタファーである。自我を保ちつつ、全体に調和する。牛である吾輩には、人間社会のそうした微妙なバランス感覚は理解しがたいが。
「チャーシューは大きく薄くそして柔らかだ」
ご主人が感嘆の声を上げた。吾輩は複雑な心境であった。豚肉を褒めるご主人の横で、いずれ牛肉として消費される自分の運命を思う。このチャーシューもかつては生きていた。豚として、泥の中を転げ回り、餌を貪り、仲間と戯れていたはずである。それが今、薄く大きく柔らかく、ラーメンの具材として昇華している。これを悲劇と呼ぶべきか、あるいは食文化への貢献と称賛すべきか。
ご主人はしばらくスープを啜り続けた。そして、ふと顔を上げた。
「何となく酸っぱいような感覚がある。これは皆さんどう感じるのだろうか?」
酸味、それは発酵の証であり、時間の経過であり、変化の兆しである。煮干の持つ複雑な旨味成分が、舌の上で化学反応を起こしているのかもしれない。あるいは、醤油の熟成が醸し出す独特の酸味か。吾輩には判別できないが、ご主人の疑問は正当である。味覚とは主観的でありながら、ときに普遍的真理に到達する。牛の味覚では草の甘味しか分からないが、人間の舌は実に繊細な楽器である。
「次回は六厘舎にもリベンジしたい。並びを覚悟だな」
ご主人が満足そうに呟いた。吾輩は内心、行列に並ぶという行為の不条理さを考えていた。美味なるものを求めて時間を犠牲にする。それは人間という種の特権であり、同時に呪いでもある。牛は牧草があれば満足する。しかし人間は、満足を求めて不満足な時間を過ごす。
あぁ東京地下街の夜はふけっていく。
煮干の香りが鼻腔に残る中、吾輩とご主人は店を後にした。地下街の蛍光灯は、昼も夜も変わらぬ光を放っている。太陽も月も届かないこの地下世界で、人間たちは麺を啜り、スープを飲み、そして束の間の幸福を得る。
吾輩は牛である。いつか肉になる牛である笑。
オーマイガー!
投稿者プロフィール