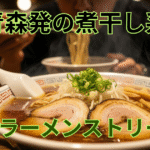春の陽光が、四谷外濠公園の桜をあまりにも見事なまでに照らし出すので、ご主人様――例の天然を絵に描いたような御仁――が、興奮冷めやらぬまま、唐突に「団子じゃなくて鯛焼きを洒落こむぞ!」と宣った。この愚鈍なご主人にとって、花見の後の甘味など、ただの糖質補給に過ぎないのだろうが、吾輩にとってはそうはいかない。この四谷という街は、その無骨な佇まいの奥に、例えば餃子酒場の喧騒や、

たけだの静かなる旨味といった、

人間たちの食欲と業が渦巻く美食の聖域である。その一角に、魚の形をした菓子が、七十余年の時を超えて存在し続けている。
吾輩は、牛という種族の持つ特権的視点から、この「たいやき わかば」という存在を哲学的に考察せねばならない。

店の中へ。行列を捌く効率性を潔く捨て去ったような、古き良き空間。幸いなことに、ここは持ち帰りだけでなく、奥の中でじっくりと味わえるスタイルを持っている。人間たちの、刹那的な美意識とはかけ離れた、永続的なる「和」の精神が、この空間には満ちている。
吾輩が席に着くや否や、ご主人様は早くもその天然ぶりを発揮し、声を潜めるどころか、店内にかろうじて響くトーンで独り言を始めた。

 ご主人
ご主人いやあ、しかし、外濠の桜は本当にきれいだったね。あの、満開から散り際に移る、あの淡いピンクの無常感がさ、たまらないんだよね! 桜ってのは、美しさの裏に『儚さ』っていう深すぎる哲学を隠してるんだよ。ところで、このたい焼きも、いつかはお皿の上から消えてしまう。儚いものって、なんでこんなに魅力的なんだろうね?
相変わらずの浅薄な「無常論」に、吾輩は心の中で嘆息する。儚いのではない、ご主人。それは、有限であるがゆえの「真摯さ」なのだ。
この「わかば」の鯛焼きが、なぜ東京三大たい焼きの一角を占めるに至ったか。それは昭和二十八年(1953年)の創業当時から貫かれる**「一丁焼き」**という製法に、人間の「誠実さ」が宿っているからに他ならない。一つの型で、一匹ずつ焼き上げる。大量生産の効率性とは対極にある、この原始的なまでの手仕事こそが、この鯛の「個」を確立しているのだ。
そして、運命の瞬間が訪れた。
「こ、これは…! 」


ご主人様の奇妙な雄叫びと共に、眼前に置かれた一匹の鯛。
吾輩は、その焦げ目も香ばしい薄皮を静かに見つめる。ご主人様は熱いと騒ぎながら、すでに頭から齧りつき、その感動をそのまま垂れ流し始めた。



うわぁ、皮がパリッパリだ! そして、この餡子、頭から尻尾まで、ぎっしり詰まってるよ! 塩気が効いてて、甘さがくどくない。あずきがぷりっぷりで、まさに生きている餡子だ!
牛である吾輩にとって、鯛の形は単なるメタファーに過ぎない。重要なのは、その「中身」だ。ご主人様の言う通り、その自家製の餡子には、北海道産小豆の真摯な粒が、ふっくらと膨らんで、互いを尊重し合いながら凝縮している。このぷりっぷりのあんこの存在感こそが、この鯛焼きを単なる和菓子から「作品」へと昇華させている。
この餡子の塩気。それは、甘美な人生の奥底に潜む、現実の苦味であり、認識のアイロニーだ。甘さだけでは、この世界は描けない。初代から守り抜かれた「尻尾まで餡子」という美学は、演劇評論家・安藤鶴夫氏がかつて見抜いた「主人の仕事に『人間の誠実さ』を味わった」という核心そのものだろう。尻尾の先まで手を抜かないという美意識は、まさに誠実さの具現化だ。
吾輩は静かに考察する。



人間は、なぜ魚の形に豆を詰めて焼くのだろうか? それは、魚のように大海を泳ぎ、自由を渇望する自己の願望を、甘く、噛み応えのある現実(あんこ)で満たしたいという、深層心理の表れではないか?
このわかばの鯛焼きは、決して儚い無常ではない。これは、変わらぬ製法と、変わらぬ誠実さという、人間が到達しうる「永遠」を象徴している。四谷の桜が今年も散り、また来年咲くように、この鯛焼きもまた、人々の記憶と味覚の中で、永久に「わかば」として存在し続けるだろう。
吾輩の食通としての結論は一つ。
この一匹の鯛は、ご主人様の「儚い」だの「きれいだ」だのという浅薄な感想を遥かに超えて、「いかに生きるべきか」という、深遠なる問いかけを、塩気と共に吾輩の舌の上に突きつけてくるのだ。
牛である吾輩は、静かに、そして皮肉な笑みを浮かべながら、この甘く哲学的な問いを咀嚼し続けた。
投稿者プロフィール


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f6290dd.3ade2761.4f6290de.98d35bd5/?me_id=1383666&item_id=10000010&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff343684-akiota%2Fcabinet%2F1007460lp_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)